ある一群は,「ん? 人生の意味? なんだろうか? 答えがあるなら教えてもらいたい」という気持ちになってしまう。そこで質問者から間髪入れず,「歴史上,もっとも信頼されてきたこの経典によれば...」と“権威”らしいものをつきつけられ,「ふむふむ,何て書いてあるのだろう。知るだけならいいだろう...」と,インストールを許可してしまうのである。そして,その“権威”が示す“人生の目的・生きる意味”に支配されるようになり,心身共に奴隷が完成してゆく。
別の一群はどうだろうか?
その前に,この記事のタイトルの答えを先に述べてしまおう。
人生の意味について,アドラーはシンプルにこう答えている。“人生に意味などない。人は意味のために生きるのではない”と。
洗脳されやすい,最初の一群のタイプの脳にとって,この格言は意外に感じられるにちがいない。人生という壮大な行程は「意味」や「目的」に沿って進むものではない,「意味」や「目的」という言葉・概念をもってしても方向付けられないほど,人生というものは壮大で重いものだ,という真理が提示されているのだ。
ところでなぜ,人は「人生の目的や意味」に関心があるのだろうか。
これもよくよくその心理を分析すると,その多くは,本当に人生の意味を探求したいというわけではなく,“自由とは何か”という人間の本質的な問いの単なる裏返しに過ぎない場合が少なくない。
つまり,何千年にもわたってつづいてきた封建的・支配的時代が終わって,ここ数十年でようやくたどりついた自由主義社会(それが本当に自由かどうかは別として...)にいきなり放り出された人類にとって,それにすぐに適応できる人もいれば,「自由? いやいや,そんなものよくわからないから,自分がどうすればいいか,何をやればいいか,だれかが指導して(支配して)くれれば楽なのに...」という自発的自由放棄というか,自由もてあまし組とも言える一群が相当数発生してしまったのである。
封建的・支配的時代においては,住むところ,仕事,結婚相手までだれかに決められたり制限されたりしてきた。当然,それに対する反発やいらだち,悲しみが生じただろう。それらの経験から,改革意識に燃えた人が人間の本質的な欲求である「自由」という概念に気づき,自由を獲得しようと命がけの努力を重ねてきたのもまた事実だ。
ところが,いざ自由がもたらされ,まさに自由主義社会ともいえる時代が訪れると,はて? と立ち止まる人たちが現れた。住むところも自由,なにを楽しんでも自由,だれと結婚しても自由,なにを信仰しても自由だし,どんな政治活動や表現活動をしても自由,なにを聞いても自由だし,なにを学んでも自由,どうぞ自由をお楽しみください!... と言われると,その“自由”があまりにもひろすぎる概念でありすぎて,何をしていいかわからなくなるのだ。“この自由をどう活用したらいいのか教えてほしい,何を信じ,だれを友にして,何をしたらいいのか,指導してほしい”という欲求はそこから来るのだ。
では,別の一群,すなわち,自分が虫かごから大草原に放たれて自由になったことを認識できるタイプの人にとって「人生の目的とは何でしょうか?」との問いはなんらかの影響を与えるものなのだろうか。彼らは大草原をくまなく全部知り得た虫などいないことをよく知っている。“答えを持っている”と称する虫がいたとしても,しょせんは池のほとりの群生地の範囲内だけはくまなく知り得た虫が「ここでこう生きるのが最善だよ」と教え得る程度のものだとわかっているのだ。
だから,たまたまそこが良さげであればそこに居を定めるかもしれないが,そうでなければ,彼らはまた,大草原の探検をつづけるのだ。大いなる自由に抱かれながら...
アドラーもその一人であったに違いない。彼は,この壮大な自由を常に認識しつつ生きることの益について我々に気づかせ,ふたたび封建社会に戻ることなく,自由を大いに活用して人生を歩むことの普遍性を教えている。そのことがひとりひとりにとって納得のいく答えに至る行程であり,のちに「人生を返せ」と人を責めなくてもよい生き方であると説いているのだ。
|
|
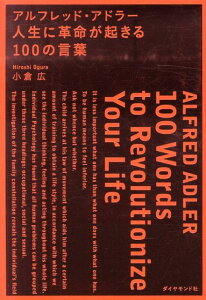





![【楽天ブックスならいつでも送料無料】オーパーツ(1) [ 南山宏 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f6616%2f9784265026616.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f6616%2f9784265026616.jpg%3f_ex%3d80x80)



![【楽天ブックスならいつでも送料無料】岩波アメリカ大陸古代文明事典 [ 関雄二 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f0008%2f00080304.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f0008%2f00080304.jpg%3f_ex%3d80x80)
![【楽天ブックスならいつでも送料無料】洗脳原論 [ 苫米地英人 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f3933%2f39336116.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f3933%2f39336116.jpg%3f_ex%3d80x80)
![【楽天ブックスならいつでも送料無料】乗っ取られた聖書 [ 秦剛平 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f8769%2f87698820.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f8769%2f87698820.jpg%3f_ex%3d80x80)